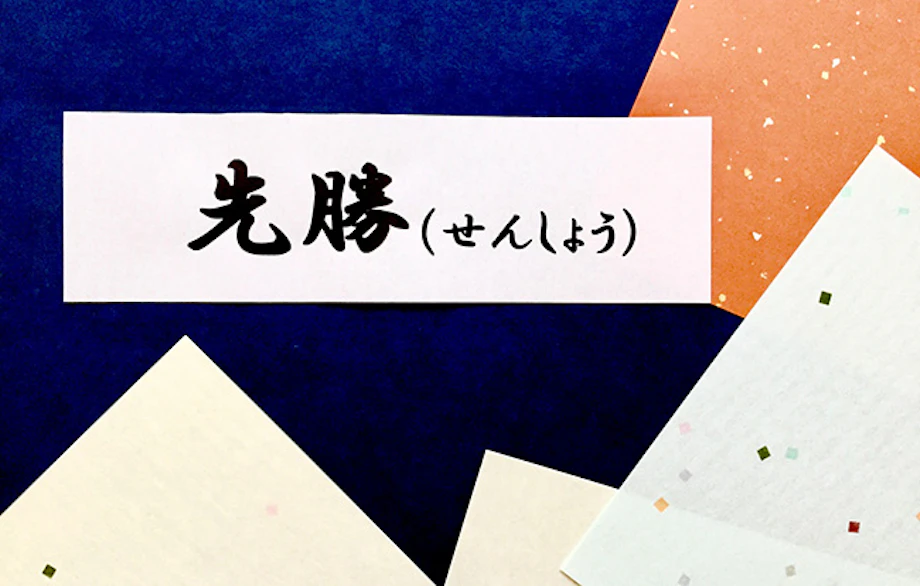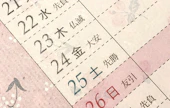法事の日程を決めるに当たり、「先勝は法事に適しているのか」と疑問を抱く方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、「先勝の法事は宗教上問題がないのか」といった疑問以外にも、六曜と法事の日程決めにおける関係性について解説します。
六曜の基礎知識に加えて、法事の日程決めの段取りや注意点も分かる内容です。法事を営むに当たって、日程決めでお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。
<この記事の要点>
・六曜と仏教には関連性がないので、先勝の日に法事をおこなっても問題ない
・友引や大安に葬儀を行うことをよく思わない方もいるため、配慮が必要
・年忌法要を命日当日に行えない場合は、日程を前倒しにする
こんな人におすすめ
法事の日程調整でお悩みの方
六曜と仏教の関係について知りたい方
六曜のそれぞれの意味を知りたい方
先勝とは?先勝以外の六曜に関する基礎知識
六曜は、日時・方角から吉凶を占う「暦注」のひとつです。鎌倉時代から室町時代に中国から伝えられ、一度は廃れたものの、明治時代以降から六曜の文化が根づきました。六曜では日ごと、1日における時間ごとの吉凶を占います。
六曜という名前の通り、先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口の6種類です。六曜を記載したカレンダーやスケジュール帳で、「どの日付にどの六曜が割り振られているか」を確認できるでしょう。以下の表の通り、六曜はそれぞれ異なる意味を持ちます。
| 六曜それぞれの意味 | |
| 先勝 | 「先んずれば勝つ」という意味を持ち、「午前は吉、午後は凶」と考えられている |
| 友引 | 大安に次いで縁起が良く、「友を引く」という漢字により慶事に適した日とされているものの、葬儀の日として避けられている |
| 先負 | 「先んずれば負ける」と先勝とは逆の意味を持ち、「午前は凶、午後は吉」と考えられている |
| 仏滅 | 「仏の功徳が滅するほどの大凶日」という意味から、六曜で最も縁起が悪いと日と考えられており、慶事は避けられている |
| 大安 | 六曜でもっとも縁起が良く、慶事を執り行う日として選ばれる |
| 赤口 | 午後13時だけが吉、それ以外は凶」と考えられている |
日曜日から土曜日まで決まった順で進む七曜と同様に、六曜の移り変わりは「先勝→友引→先負→仏滅→大安→赤口」という順です。
旧暦では各月1日に特定の六曜が割り振られていたため、周期が不規則でした。現在のカレンダーでは各月1日に特定の割り振りがなく、六曜の順に従って割り振られる傾向にあります。
先勝の法事は問題ない?六曜と法事の日程における関係性
突然の別れを受けて葬儀の日程を決める場合でも、六曜の友引は可能な限り避けることが多いでしょう。法事の日程決めにおいては、六曜を加味する必要はあるのでしょうか。こちらの項目は、六曜と法事の日程決めにおける関係性が分かる内容です。
六曜は仏教とは無関係!先勝に法事を営んでも問題ない
漢字から「故人の友人にも不幸がある」と考えられている友引は、葬儀の日取りとして好ましくないとされています。多くの火葬場では、弔事が避けられる友引に定休日を設けている点でも、葬儀の日取りとして友引は適していません。
しかし、六曜は仏教とは直接的に関係のない考え方です。法事の日程決めでは、基本的に六曜を考慮しなくても問題ありません。先勝に法事を営んでも宗教上の問題はありませんから、参列者の予定が合えば先勝で法事を営みましょう。
先勝の法事は午前中がベスト?時間帯には決まりはある?
先勝は、「午前は吉日、午後は凶日」と考える六曜です。しかし、法事と六曜は宗教上の直接的な関係がないため、「先勝の法事は午前中に済ませなければならない」と考える必要はありません。また、法事を営む時間帯は、都合に合わせた調整が可能です。
法要の後に会食を設けることがあるため、法事は午前10時~午前11時ごろから開始する傾向にあります。
しかし、「法事は午前中から始めなければならない」というマナーはありません。僧侶や参列者の予定に合わせて、法事を午後に設定しても問題ないでしょう。平日に法事を営む場合には、仕事の後に参列できるよう、夕方から開始する配慮も必要です。
法事の日取りでは友引と大安に注意
六曜と仏教は原則無関係ですから、法事の日程決めでは六曜を考慮する必要はありません。ただし、友引と大安の法事に対しては、よく思わない方がいます。
友引では葬儀を避けることから、法事も避けたほうがよいと考えるからです。大安に関しては、「もっとも縁起が良い日に法事を営むとは、故人に対して失礼ではないか」という考えもあります。
また、縁起が良い大安は、慶事(結婚式や入籍など)に適しているとされる六曜です。より多くの人に参列してもらいたい場合には、誰かのお祝い事と法事が重複する可能性もある大安は避けたほうが無難といえます。
法事の日取りは家族や親族、参列者の考えに配慮する
法事における六曜の考え方は、家族や親族、参列者によってさまざまです。「六曜は仏教に関係のない考え方だから」と、独断で法事の日付を決定するのは好ましくありません。
法事の日程で六曜を気にする人がいれば、その人の考えに配慮しましょう。参列者全員が納得できる日取りにすることが、施主の役割のひとつだからです。
法事の日取りで悩んだ際には、信頼できる家族や親族、寺院に相談した上で日付を決めることをおすすめします。親族や参列者の考えに配慮することは、トラブルを回避して良好な関係を維持する上でも大切です。
基本的に法事は祥月命日に!日程変更における注意点
法事を営む時期は、故人が亡くなってから経過した日数・年数で決まっています。しかし、予定通りの日程で法事を営めるとは限りません。
法事の日程を調整する場合には、故人の祥月命日を過ぎないようにするのがマナーです。また、法事の日程を祥月命日から変更する場合には、寺院への相談も必要となります。
一周忌以降は祥月命日に執り行う
僧侶に読経を上げてもらう「法要」の後、参列者や僧侶と会食の時間を共にする「お斎(おとき)」が組み合わさった儀式が法事です。故人の供養を目的とする法要は、忌日法要と年忌法要の2種類に大別できます。
故人が亡くなった月日(祥月命日)から7日ごとにある忌日のうち、特定の日に営まれるのが忌日法要です。
主な忌日法要としては、初七日法要・四十九日法要・百箇日法要が挙げられます。宗教観によって差があるものの、「死後49日の経過で故人は成仏する」と考えられている四十九日法要は特に重んじられている忌日法要のひとつです。
年忌法要とは、故人が亡くなってから1年後(一周忌)、故人が亡くなってから2年後(三回忌)と特定の年数ごとに執り行われます。一周忌以降の年忌法要の日程としては、故人の祥月命日が最適です。
日程調整では祥月命日を過ぎないよう注意
年忌法要を営む年の祥月命日が平日の場合、仕事や学校などの都合により人が集まりにくいでしょう。故人をしのぶ儀式である法事は、より多くの人が集まったほうがよいとされています。
故人の祥月命日に法事ができればベストですが、多くの人が集まれるよう週末や祝日にずらす配慮も必要です。法事の日程調整では、祥月命日を過ぎないよう、繰り上げの日取りで決めることがマナーと考えられています。
法事の日程調整では寺院にも要相談
法事の日程を決める際は、菩提寺(ぼだいじ)に最初に相談しましょう。僧侶を招いて読経を上げてもらう場合は、僧侶のスケジュールも調整してもらう必要があるからです。
自宅以外で法事を営むのなら、寺院や会館などの会場の空き状況も日取りに大きく関わります。法事の日程調整は、できるだけ早いタイミングで寺院に相談しましょう。相談するタイミングが早いほど、日程の希望が通りやすくなります。
複数の法事が同年内にあるなら併修という方法も
年内に複数の法事が重複する場合、日程調整をはじめとした法事の準備に追われるでしょう。参列者や施主側の年齢、年忌法要の種類によっては、同年内にある複数の法事をまとめて営む「併修(へいしゅう)」も選択肢に入るでしょう。
こちらの項目では併修に関する基礎知識に加えて、併修で営む場合の注意点についてご紹介します。
併修とは?併修における日程の決め方
合斎(ごうさい・がっさい)とも呼ばれる併修は、同年内にかぶった複数の年忌法要をまとめて営む方法です。ひとりひとり個別で法事を営むのがベストですが、施主や参列者の年齢によっては法事の実施・参列自体が体の負担になり得ます。
肉体的な負担だけでなく、経済的なコストにも配慮しつつ法事を営める点が併修のメリットです。
併修の場合、日程は祥月命日が1番早い人に合わせましょう。併修においても、祥月命日を過ぎた法事の実施は故人に対して失礼に当たるからです。8月27日にある祖父の十三回忌、10月3日にある祖母の七回忌で併修する場合、より早い祥月命日の8月27日に合わせて日程を調整します。
七回忌以降の年忌法要が併修の対象
併修として法事を営めるのは、七回忌以降の年忌法要に限られています。七回忌より前の年忌法要(一周忌と三回忌)は、併修ではなく単独で法要を営んで故人をしのんだほうがよいと考えられているからです。
ただし、「何回忌から併修としてもよいか」の考え方には幅があり、「三回忌以降の年忌法要なら併修でもよい」とする意見もあります。
また、家族の年齢を考慮して、三回忌までの年忌法要についても併修を考えることもあるでしょう。何らかの事情により三回忌までの年忌法要も併修を希望する場合には、菩提(ぼだい)寺への相談をおすすめします。
併修の際には親族や寺院と要相談
「併修はなるべく避ける」といった考え方もあり、併修に対するスタンスは宗教・宗派、地域の慣習によってさまざまです。
菩提寺が併修に対応しているとも限らないため、併修を検討する場合は事前相談が必要となります。また、家族や親族によっても併修の捉え方が異なるため、「併修とするかどうか」は話し合いで決めるようにしましょう。
法事の日程はいつまでに決めておく?案内のタイミングとは
僧侶への依頼や案内状の手配など、法事では数多くの事前準備が必要です。日程を決めなければ、さまざまな事前準備を進められません。スムーズに準備できるよう、法事の日程決めは余裕を持って行うことが大切です。法事の施主が知っておきたい、日程決めの期限となる目安の他、法事を案内するタイミングについてご紹介します。
祥月命日の2、3ヶ月前には法事の準備を始めよう
僧侶への依頼や会場の予約(自宅以外で執り行う場合)、参列者分のお斎の手配など、法事を営むにはさまざまな準備が必要です。
僧侶や参列者の都合が付きやすいよう、なるべく早いタイミングで法事の日程を決めます。年忌法要の場合には、祥月命日の2ヶ月~3ヶ月前、遅くても祥月命日の1ヶ月前には日程決めに着手しておきましょう。
さまざまな事前準備を計画的に進めるに当たり、まずは法事の日程を決めなければなりません。法事の日程が決まらなければ、参列者に案内状を送付できないからです。具体的な参列者数が分からなければ、人数分が必要になる会食・土産・茶菓子などの手配もできません。
法事の日取りが決まったら早めに案内する
読経を依頼する僧侶の都合がついたり、会場の手配ができたりと法事の日程が決まったら、早めに参列者に案内しましょう。
案内状を出す人の範囲も、事前に決めておく必要があります。法事の予定日の2週間前には出欠が確認できるよう、予定日の1ヶ月前には関係者に案内状を送付しましょう。
法要の後にお斎を設ける場合には、その旨を案内状に記載します。参列者数が判明したら、当日渡す香典返し(または返礼品)や会食の手配に進みましょう。
参列者数分の用意が求められる香典返しや会食に関しては、いつまで数の変更が可能なのかを確認しておくと急な変更があった際にも安心です。
併修の場合にはその旨を案内時に伝える
併修で法事を執り行う場合には、法事の日取りが故人の祥月命日と大きく異なることがあります。参列者を混乱させないよう、案内の際に「誰の年忌法要の併修であるか」を伝えておきましょう。
家族と親族だけで併修とする法事を営む場合、案内状を用意せず電話やメッセージアプリを用いて連絡するケースも珍しくありません。電話などで法事の日程を伝えるときに、一緒に併修である旨も伝えておきます。案内状で参列者に伝える場合には、併修とする故人全員分の氏名、年忌法要を分かりやすく記載しましょう。併修とする年忌法要の中で回忌数が少ない順に、氏名とそれぞれの年忌法要を書きます。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
六曜と仏教は直接的に関係のない考え方のため、法事の日程では六曜を気にする必要はありません。しかし、友引や大安の法事設定を好まない人もいます。
関係者の中に法事の日取りで六曜を気にする人がいるのなら、その人の意見を考慮したほうが無難です。また、多くの人が参列できるように、祥月命日以外の日程で調整する対応も求められます。
関係者の年齢によっては、併修も選択肢に入るでしょう。どのような形で法事を営むにしても余裕を持って準備できるよう、なるべく早めに日程を決めておくことが大切です。
なお、今回は一般的なところを紹介しましたが、六曜については、地域、寺院、親族ごとに異なる風習が根づいていることがあります。法事でも周囲の事情を十分に確認しながら日程決めをしましょう。
法事の日程決めでお悩みの場合には、小さなお葬式のお客さまサポートダイヤルにご相談ください。
法事・法要以外にも、葬儀全般に関する悩みや疑問があれば「小さなお葬式」へご相談ください。知識豊富な専門スタッフが24時間365日サポートします。


御仏前は「仏となった故人の前に供えるもの」という意味です。ホゥ。