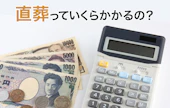故人には戒名が付けられることが一般的ですが、宗教儀式を行わない直葬では、故人に戒名を付けるべきか迷うところでしょう。また、まとまったお金が必要になることから、戒名なしで済ませてよいか悩んでいるという方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、故人に戒名を付けるべきか、菩提寺の有無に応じた判断について解説します。
<この記事の要点>
・直葬はシンプルな葬儀形態のため、戒名は必ずしも必要ではない
・直葬で戒名をつけたい場合は、事前に菩提寺に相談しておく
・通夜や葬儀をする場合は基本的に戒名が必要
こんな人におすすめ
直葬で戒名を付けてもいいのか気になる方
戒名のつけ方について知りたい方
戒名が必要になる場合について調べている方
直葬でも戒名は付けるべき?
直葬とは自宅や病院など、故人を亡くなった場所から直接火葬場に送ることです。通夜や葬儀などの宗教儀式を省くシンプルな葬儀形態ですが、戒名については付けるべきか悩む方も多いでしょう。ここからは、直葬における戒名の扱い方について解説します。
必ずしも付けるものではない
戒名は必ずしも必要ではありません。たとえば、無宗教のお墓に入る場合は基本的に必要ないでしょう。しかし、お墓がお寺にある場合は、納骨の際に戒名を付けるのを条件とするお寺もあるので注意が必要です。
死後に戒名を付けるのは僧侶にしかできません。戒名が必要ということであれば、生前にお寺に相談しておくとよいでしょう。
直葬の場合は付けない人も多い
直葬は多くの参列者を招待することなく、親しい関係者のみ少人数で執り行います。シンプルな葬送方法なので、戒名も必要ないと考える遺族もいるでしょう。
また、宗派や地域によって異なりますが、戒名には20万円~60万円ほどの戒名料が必要です。費用を抑えるために直葬を選択した場合、負担の大きい戒名を付けないケースも珍しくありません。
<関連記事>
【第1回調査】直葬にかかる費用相場(全国編)
直葬で戒名を付ける方法
直葬を選択したけれど、戒名は付けたいと考える方もいるでしょう。直葬でも希望すれば戒名を授与できます。しかし、菩提寺の有無で手続き方法が異なります。ここからは、菩提寺の有無に応じた戒名授与の方法を紹介します。
菩提寺がある場合
菩提寺への納骨を希望する場合は、前もって直葬について相談しておきましょう。お寺は宗派に基づいた考えなどを理由に、直葬を認めないこともあるからです。
直葬を執り行う前に戒名を付けてもらえるかを確かめて、同意を得たら正式な依頼をしましょう。菩提寺に何の相談もなく直葬をしてしまうと、納骨を断られるなどのトラブルにもつながるので注意が必要です。
菩提寺がない場合
菩提寺がない場合や霊園への納骨を希望する場合は、葬儀社に相談してみましょう。自身の宗教や宗派にあった寺院を紹介してもらえば、スムーズに戒名の依頼が可能です。僧侶の手配まで葬儀社に一任してもよいでしょう。
いざというときに「家族の宗派が分からない」というケースも見られます。また「実は菩提寺があった」「菩提寺を変更していた」ということも稀にあります。菩提寺の有無や宗派については、あらかじめ家族や親戚に確認しておくとよいでしょう。
<関連記事>
直葬で納骨が断られる可能性がある!断られたときの対処法は?
小さなお葬式で葬儀場をさがす
戒名について知っておくべきこと
戒戒名は宗派により種類が異なり、ランクもあります。高い位の戒名を付ける際の条件や金額なども気になるところでしょう。ここからは、戒名の定義や種類、ランクをわかりやすく紹介します。
戒名とは?
戒名とは故人に付ける名前のことで、仏の弟子となった証明です。本来は仏門に入ったお坊さんが戒律を受け入れた弟子に与えていました。現在の戒名には、「故人がこの世に生きたことをたたえ、安らかに天に昇っていただく象徴」という意味が込められています。主に菩提寺の住職や僧侶が命名します。
元来戒名は、どんな地位にある人でも二文字であることが原則でした。しかし、現代社会ではランクなどの関係により、漢字10文字~15文字での構成が主流です。
宗教によって名前が違う
戒名は宗派で呼び方が異なります。たとえば浄土真宗での呼称は「法名」です。「釈号」として頭に「釈」を付け、お釈迦様の弟子と証明します。
日蓮宗では「法号」と呼ばれ、途中に「日号」の「日」を入れるきまりがあります。また、浄土宗なら「誉号」が必要なことから「誉」が入るなど、宗派で戒名の扱いは異なります。
戒名にもランクがある
戒名にはランクがあり、ランクは故人の生前の活動やお布施などできまります。ただ、このような考え方は従来ではタブーとされてきました。仏の世界で人間は平等と見なされており、位による棲み分けはありえなかったためです。
しかし、現在は仏教貢献の証である「院号」、悟りを得た人への「道号」が戒名の前に付けられ、後ろには性別、年齢、地位に応じた「位号」が伴います。このように故人のステータスに応じて戒名が変わるのが現在の慣習です。基本的に文字数が多いほどランクが高い傾向にあります。
お布施の金額によって戒名のランクが変わる
お布施は金額に幅があるのが特徴で、故人のお寺に対する生前の貢献度やお布施の金額によって戒名のランクが変わります。「院居士」「院大姉」などのランクの高い戒名料は100万円以上が目安となります。
また、戒名のランクには注意点があります。たとえば、同じお墓に入っている先祖よりもランクの高い戒名を付けることはできません。夫婦のような対等な家族関係で位が異なるのも好ましくありません。知らずにマナーを破らないように、事前にお寺に相談しましょう。
戒名が必要となるとき、ならないとき
直葬以外の葬儀形式の場合であっても、戒名の必要性は状況によって異なるので、事前にしっかり検討することが大切です。たとえば、通夜や葬儀を執り行う場合は必要ですが、樹木葬や海洋散骨などの自然葬であれば付けないこともあるでしょう。
また、寺院墓地に納骨する際は戒名が必須ですが、公営・公園墓地の場合は戒名なしで納骨できるところも増えてきています。
戒名が必要な場合
通夜や葬儀をする場合は基本的に戒名を付けます。葬儀では僧侶を呼ぶので、必ず戒名を授ることになります。その際は、相応のお布施が必要となることも理解しておきましょう。戒名に限らず、故人の意向をくみ取り、周囲としっかり相談した上で葬儀の手続きを進めることが大切です。
また、寺院墓地に納骨する場合も戒名を付ける必要があります。寺院墓地は事前に使用規則をもらって契約するのが一般的で、葬儀・告別式・回忌法要などのきまりがあります。葬儀と戒名授与はセットとなっているため、勝手に直葬したり、よその寺院で葬儀や戒名授与をしたりすると契約違反に問われる可能性もあります。
戒名が不要なケース
自然葬では一般的に戒名は不要とされています。自然葬とは、遺骨を自然に還す葬送方法で、樹木葬や海洋散骨などがあります。自然葬では戒名を付けないことが多いでしょう。
しかし、最近はお寺が樹木葬を行うケースも増えており、戒名を規則化しているところもあります。戒名について悩んでいる場合は事前に確認しておきましょう。
また、公営・公園墓地は戒名なしで問題ないケースが多いといえます。きまった宗派がなく、檀家のような考えもないので、キリスト教徒やイスラム教徒の遺骨もを受け入れています。多種多様な宗派を受け入れる関係上、戒名という概念自体あまり気にされることはないでしょう。
<関連記事>
自然葬とは?種類や費用について
小さなお葬式で葬儀場をさがす
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
直葬における戒名の必要性は、葬儀の有無や納骨先などによって異なります。戒名を納骨の条件としているお寺も少なくないので、菩提寺がある場合は前もって必ず確認しておきましょう。勝手に直葬してしまうとトラブルになる恐れもあります。戒名なしでの直葬も珍しくありませんが、生前の本人の希望を確認しながら慎重に検討しましょう。
「小さなお葬式」では、高品質かつ低価格な葬儀サービスをご提供しております。戒名に関するご相談も承っておりますので、何かお困りごとがある際には小さなお葬式までぜひご相談ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


関連記事
直葬にお布施は必要?金額の相場や渡す際のマナーを紹介します
直葬を行う前に知っておきたいこと
「直葬」とはどんな葬儀形式?費用の相場や注意点とは?
火葬式(直葬)の費用相場と安くする方法
直葬の香典はどうする?金額の相場や渡し方など気を付けるべきマナーをチェック
直葬での服装は?平服と言われたときの理想の格好やNGな格好も紹介
直葬でのマナーまとめ!服装・香典・直葬を行うときの注意点とは?
直葬で納骨が断られる可能性がある!断られたときの対処法は?
直葬と密葬の違いは?それぞれの葬儀に決める理由や流れとは
直葬(火葬式)の割合は?直葬が選ばれている理由
よくある質問
戒名を付けないと起こるトラブルとは?
戒名を付ける際のお布施の目安は?
生きている間に戒名を付けられる?
生前戒名のメリットとは?
戒名は僧侶しか付けられない?
自分で戒名を付けるメリットとは?

遺言者の意思や希望を書面に反映し、公文書として承認された遺言書が「公正証書遺言」です。ホゥ。