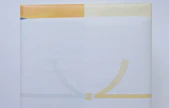法事の際にどんなものを用意すれば良いのかよく知らないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
法事の際の持ち物などについて、故人やご遺族に失礼のないようにマナーやルールをしっかり把握しておきましょう。施主やご遺族にとっても、故人や参列者に失礼のないようマナーやルールをチェックすることをおすすめします。
今回は、参列者、遺族側それぞれの持ち物や準備が必要なものについて解説します。いざというときに迷うことのないよう、確認しておきましょう。
<この記事の要点>
・参列者は、香典・お供え物・数珠を持参する
・遺族は、法事に必要な費用(お布施や会場使用料)・遺影・返礼品などを用意する
・四十九日の法要では、特に「本位牌」と「埋葬許可証」を忘れないように注意する
こんな人におすすめ
法事に参列する際の持ち物を知りたい方
四十九日法要に必要なものを知りたい方
自宅で法事を行う際の準備物を知りたい方
【参列者側】法事に用意するものと持ち物リスト
まず、参列者側の法事の際に用意したい持ち物をご紹介します。マナーやルールを理解せずに準備をすると失礼になってしまうこともあるので、注意が必要です。故人に対してだけでなく、ご遺族への配慮としても大切なのでマナーやルールを確認しておきましょう。
香典またはお供え物
参列者は香典やお供え物を持参して参列します。
香典やお供え物の金額目安は5,000円~1万円程度です。ただし、地域や故人との関係性によっても変わってくるので注意しましょう。香典とお供え物の両方を用意するというケースも少なくありません。故人との関係性に応じて選択するのがおすすめです。
数珠
数珠はお焼香の際に使うので、必ず持参するようにしましょう。数珠は身を守る効果がある仏具なので、原則として貸し借りは避けましょう。持っていない方は購入して持参するのが無難です。
親族の場合も持ち物は同じ
親族の場合も、持ち物はほとんど同じです。親族と一般参列者の大きな違いは、香典の金額目安にあります。香典の目安は1万円~5万円程度と、参列者よりも高額になるのが一般的です。
ただし、金額目安は故人との関係性によって変わってきます。不安な場合は自分と立場の近い方に金額を相談し、それに合わせると安心です。
お供え物が必要かどうかは地域によって異なる
お供え物が必要かどうかは、地域性によっても大きく異なります。基本的には、お供え物が必要であることが多いですが、地域によっては必要としない場合もあります。必要がないのに持参してしまうとかえって失礼にあたる可能性がありますので、十分注意してください。
【遺族側】法事に用意するものと持ち物リスト
ここでは、遺族側で法事の際に用意するものをご紹介します。一般参列者として参加する機会はあっても、遺族側として葬儀に参列する機会はそれほど多くはないでしょう。
いざというときに困らないように、ルールやマナーを理解しておくと安心です。ここでは、法事の際に遺族側が用意するものについてご紹介します。
法要に必要な費用(お布施など)
遺族側は、お布施などの費用を用意します。読経してくれる僧侶に支払うお金などは、当日に手渡しとなるケースが多いので、忘れずに持参しましょう。お布施の目安は地域によっても大きく異なるので、近くの方に相談するなどして把握しておくと安心です。
会場使用料やお花代なども当日精算となるケースが多いので、忘れずに持参しましょう。
遺影
故人の遺影も欠かせません。遺影は祭壇に飾られる故人の写真であり、参列者が生前の故人を偲びながら見送るために重要です。
遺影は、故人らしい表情の写真を選ぶのが好ましいとされています。写真の選定は慎重に行いましょう。
また、参列者が故人の目を見てお別れがしやすいように、カメラ目線の写真を選ぶのが一般的です。遺影も当日持参するので、忘れないよう準備しましょう。
埋葬許可証
火葬した遺骨を埋葬するための許可証です。この許可証がないと埋葬ができません。分骨する際は、場所ごとにそれぞれ許可証が必要になるので注意してください。
証明書を紛失してしまった場合には再発行が可能です。埋葬までに間に合うよう、必ず手元に準備しましょう。
本位牌
本位牌は四十九日までに作られるので、葬儀や通夜のタイミングでは用意できません。そのため、本位牌が必要になるのは四十九日以降だと理解しておきましょう。
本位牌は故人の霊魂が宿る場所だとされているため、法要の際に欠かせません。忘れずに持参してください。
返礼品(香典返し)
遺族側で準備が必要になるのが「香典返し」です。香典返しは、参列者にいただいた香典に対してお返しとしてお渡しするもので、一般的には現金ではなく品物で準備します。お茶やお菓子、カタログギフトなどを選択するケースが多いです。
香典が必要となるシーンでは、香典返しも必要となります。忘れることのないよう注意してください。
【施主】法事に用意するもの
施主は遺族とともに行動するので、特別な持ち物は必要ありません。遺族側の持ち物と同じものを用意しておけば問題ないでしょう。ただし、施主が中心となって動く場合は、持ち物に抜け漏れがないかしっかり確認しておくことが大切です。
法事別で持ち物に大きな違いはない
法事別で持ち物に大きな違いはありません。基本的には上記でご紹介した持ち物を押さえておけば問題ないでしょう。
法事を執り行う場所で変わる用意するもの
法事を執り行う場所によって、一部持ち物が変わる場合があります。法事がどこで行われるのかを事前に確認し、適切なものを用意しましょう。
自宅で法事を執り行う場合に用意するもの
自宅で法事を行う場合、一般参列者の持ち物にはほとんど違いがありません。一方、遺族や施主は準備するものがあります。
自宅で読経をしてもらうことになるので、参列者分の座布団または椅子の確保が必要です。座布団が一般的ですが、足が悪く立ったり座ったりという動作が難しい方もいらっしゃるでしょう。そのような方のために、椅子も準備しておくという配慮も必要です。
また、僧侶に自宅まで来てもらうことになるので、お車代を用意する必要があります。会食があれば、そちらにも僧侶をご招待するのが一般的ですが、僧侶が参加されない場合には御膳料もお渡ししますので注意が必要です。
会食を自宅で行う場合は、仕出し弁当やお茶などの手配も必要になります。このように、自宅で法事を行うケースでは、手配するものが多くなるでしょう。
お寺で法事を執り行う場合に用意するもの
お寺で法事を行う際に用意するものは、持ち物としてご紹介したもので足りることが一般的です。
また、会食を寺院内で行う場合は問題ありませんが、そうでない場合にはお店の予約が必要です。お寺のご住職が会食に参加されない場合には、お渡しする御膳料を用意しておきましょう。
四十九日法要の持ち物が一番多くなる?
四十九日の法要は、各法要の中でも一番荷物が多くなるので忘れ物がないよう注意したいところです。
四十九日ならではの持ち物は、上記でご紹介した本位牌と埋葬許可証です。埋葬許可証と本位牌の用意を忘れてしまった、もしくは自宅に置いてきてしまった場合、式自体が止まってしまう可能性があります。この2点は四十九日でのみ必要なので、忘れないよう注意しましょう。
【参列者側・遺族側】法事に向けて準備しておきたいマナーと心得
法事に向けてマナーやルールを確認しておくことは非常に重要です。マナーやルールを知らずに参加すると、故人や遺族に対して失礼な対応をとってしまう可能性がありますのでしっかり理解しておきましょう。
法事を僧侶に依頼するなら服装は準喪服で
僧侶に法事を依頼するケースの場合は、準喪服を用意しましょう。特別な指定がない場合、準喪服を選択しておけば間違いありません。
黒を基調とした普段着で参列する方も中にはいらっしゃいますが、普段着での参列はマナー違反です。特に、僧侶に依頼して法事を行うシーンでは準喪服を選択してください。
香典袋の書き方とマナー
香典袋の書き方やマナーは四十九日を境に変わります。四十九日より前の法事では、薄い墨で名前を記載します。一方、それ以降に関しては墨の濃さに決まりはなく、筆ペンで記載しても問題ありません。
また、中に包む金額によって適切な水引の種類も異なります。よく確認し、適切な水引がついた香典袋を購入しましょう。
お供えは施主に渡す
お供えは必ず施主にお渡ししましょう。直接自分で仏前に供えるという行為は、失礼にあたります。自分で仏前に供えたい場合には施主に許可を取りましょう。勝手にお供えするのはマナー違反なので注意してください。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
法事で用意するアイテムは独特なものが多いので、慣れていないと困惑することも少なくありません。故人やご遺族に失礼にならないよう、マナーやルールを守った立ち居振る舞いをすることが必要です。
また、遺族や施主の持ち物は一般参列者と同じではありません。式の進行を左右するアイテムも含まれていますので、持ち物の確認は入念に行いましょう。
「小さなお葬式」では法事に関するご相談を承っております。専門のスタッフによるご相談のケースに合わせたアドバイスが可能です。
法事・法要以外にも、葬儀全般に関する悩みや疑問があれば「小さなお葬式」へご相談ください。知識豊富な専門スタッフが24時間365日サポートします。何かお困りのことがあれば、まずはお気軽にご相談ください。


遺産相続が発生した場合、いかなる場合でも配偶者は相続人になります。ホゥ。