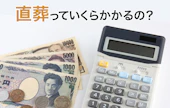近年、葬儀の形が変わりつつあります。かつては親戚や近所の方などが大勢参列し、故人をお見送りする一般葬が主流でした。しかし、時代の流れと共に直葬(ちょくそう)・火葬式を選択する人が増えてきました。一体どれくらいの割合で直葬が選ばれているのでしょうか。
<この記事の要点>
・直葬は全体の5.5%だが、増加率は26.2%であり、家族葬と共に増加傾向にある
・都市部の場合、地方よりも人との繋がりが薄いため直葬の割合が高い
・経済的事情、高齢化社会、核家族化、地域との関係性の変化により選ばれやすい
こんな人におすすめ
直葬をお考えの方
直葬の注意点を知りたい方
直葬以外の葬儀形式について知りたい方
直葬(火葬式)が行われている割合
葬儀の形態としては、一般葬を始め、家族葬、直葬、一日葬、社葬などがあります。昔は一般葬が多く行われていましたが、近年の葬儀事情は時代の流れにともない、変わりつつあります。
葬儀の形態別による割合と、増加傾向にある葬儀形態をみてみましょう。
| 葬儀の形態別割合 | 葬儀形態による増加率 | |
| 一般葬 | 63.0% | 5.4% |
| 家族葬 | 28.4% | 51.1% |
| 直 葬 | 5.5% | 26.2% |
| 一日葬 | 2.8% | 17.1% |
| 社 葬 | 0.3% | 0.3% |
※公正取引委員会の葬儀業者アンケート調査(直近5事業年度)
「葬儀の取引に関する実態調査報告書 H29.3.22」より
直葬が占める形態別割合の5.5%は少ないように見えますが、葬儀形態による増加率をみると、直葬は26.2%となっており家族葬51.1%と共に増加傾向にあります。その一方で、一般葬の割合は5.4%しか増加していないことがわかります。
直葬とは
直葬とは、通夜式、告別式は行わず、ご遺体を棺に納めたあと火葬を行う葬儀の形態です。参列者数も一般的な葬儀とは違い、ごく親しい方のみが参列し少人数で行わるシンプルな葬儀です。また、特に首都圏における直葬の割合は、増加の傾向にあります。
地域による直葬の割合の違い
直葬を行う割合を地域ごとに比較すると、都市部の方が高い傾向にあります。その理由としては、葬儀にかかる費用を節約したいという経済的な理由や、都市部だと人との繋がりが薄くなりやすいという理由が挙げられます。
地方では近隣との繋がりが強いこともあり、直葬の割合は低くなります。普段の近所づきあいもあり、近隣の人同士で一緒にお見送りする機会もあることが理由だと考えられます。
また、直葬で十分と考えている人もいれば、それだと葬儀にかける時間が少ないため寂しいと感じるといった人もいます。故人を偲ぶために適切な方法はどれなのか、そのケースごとに考えることが大切です。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
直葬が増えている理由
それでは、なぜ直葬や家族葬などの小規模の葬儀形態が増加しているのでしょう。その理由には、経済的事情、高齢化社会、核家族化、地域との関係性の変化などが挙げられます。
経済的な理由
直葬のメリットを考えた場合、最初に思うことは費用が抑えられることでしょう。実際、一般葬にかかる費用は平均121万円といわれています。経済的な面で多くの人が節約をしている中、葬儀に大きなお金が出ていくことは、一般の家計にとっては大変負担になるのです。こうした経済的事情が直葬の割合を伸ばしているといえるでしょう。事実、直葬の場合は20万~30万円程で行えることから考えると、かなり費用を抑えられます。
また、一般葬の場合、前もって参列者数を把握できないため、あとで予想以上に出費が増えてしまうケースがよくあります。直葬は前もって人数が分かっているので、費用が確定しやすくなります。
直葬が時代の変化に合っているわけ
言葉を変えれば、一般葬が社会的な時代の変化に合わなくなってきたのです。その背景には、高齢化社会、核家族化、地域とのつながりの変化に大きく関係しています。
まず、日本は高齢化社会です。高齢化が進む中、亡くなる方も高齢化しています。一般的に高齢になるほどお付き合いの数も減り、葬儀に参列する知人、友人も少なくなるので、参列者が多い一般葬の必要性がなくなります。
昔に比べて家族の形態が変化していることも、小規模の葬儀が好まれる理由の一つです。昔は2世代、3世代が同居するのはごく普通のことでしたが、都市部においては核家族世帯が多くなっています。親戚と疎遠になっている家庭も多く、近所付き合いも以前に比べると少なくなってきていることから、葬儀も身近な人のみで行うことが増えています。
また、核家族でお仏壇を家に置いていない世帯が多くなり、宗教的つながりを感じないため、葬儀にお坊さんを呼ぶ必要性を感じない方もいるようです。そうなると一般葬は選択肢に入らなくなるのです。
さらに、無縁社会で生活をしている単身世帯が増えていることも、直葬の増加につながります。無縁社会とはNHK番組から生まれた造語で、親戚や地域とのつながりを持たず、人間関係が希薄で孤立した社会をいいます。無縁社会で生活をしている方が亡くなった場合、葬儀の参列者もいないことから、直葬を行うことになるのです。
そして、直葬は少人数で執り行われるため、参列者への対応や葬儀を手伝って下さった方へのご挨拶などが不要になります。葬儀を行う側の心の負担が軽減されることも、直葬のメリットになるようです。
直葬以外の葬儀の種類
葬儀には直葬以外にもいくつか種類があります。直葬はお葬式のみで、親しい人限定で行うシンプルな形式ですが、故人の見送り方は人によって希望が異なります。
親族以外の人も交えて大人数で見送りたい方もいれば、お通夜とお葬式を1日でコンパクトに行いたい方もいるでしょう。
故人やご遺族の意向に合った形式を自由に選択できるように、どのような種類があるのかをまとめていきます。ぜひ葬儀のご参考にしてください。
一般葬
一般葬は、家族・親族のみではなく、幅広い方々に参列してもらう葬儀形式です。故人、遺族と親交のある方へ広くお知らせをして参列してもらうことで、葬儀に関わる人間関係がこじれることを防げるでしょう。
参列する人数は場合によって異なりますが、約200人~300人が目安となります。大人数で安心して故人をお見送りすることができます。
<関連記事>
【第1回調査】一般葬にかかる費用相場(全国編)
家族葬
家族葬はその名の通り、遺族のみで実施する葬儀のことを指します。ただ、実際には遺族以外にも親しい方が参列する葬儀のことも指すことが多くなっています。人数としては、30人未満が目安です。
家族葬であれば、一般葬のように大人数にお知らせする必要がなく、少人数で故人をお見送りすることができます。遺族の費用も節約できるため、経済的負担を軽減できるという点と、精神的にも落ち着いて時間を過ごせる点が家族葬のメリットです。
<関連記事>
【第1回調査】家族葬にかかる費用相場(全国編)
一日葬
一日葬は、通常二日かけて行う葬儀を一日で完了する形式のものです。お通夜、葬式、告別式を二日に分けて行うことが一般的ですが、お通夜を省略するためゆっくり故人をお見送りできます。
最近では、家族葬と一日葬を一緒に行うのが流行っているようです。家族・親族のみで行うので、親しい間柄の人どうしゆとりをもって時間を過ごせます。経済的負担と時間的な余裕ができるため、安心してお見送りできることも魅力の一つです。
<関連記事>
一日葬の費用はいくら?相場や内訳を徹底解説!
社葬
通常個人が施主となる葬儀ですが、社葬の場合は施主が会社となります。法人が施主となって葬儀を行うため、一般的な葬儀よりも人数が多く、規模が大きいという特徴があります。
なぜ社葬という形式があるのかというと、法人の創業者やオーナーが亡くなった時に、故人を偲ぶことと、継承者を社会全体に広く知ってもらうことが目的となっているからです。そうして会社の社会的地位を保つために、他の葬儀とは別に社葬を行うのです。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
直葬を行う際に注意しておきたいこと
直葬を行うには、注意すべき点がいくつかあります。あとでトラブルにならないように前もって確認しておきましょう。
家族の了解を得ておく
直葬を行う場合は、事前に親族の理解を得ておく必要があります。一般的な葬儀の形態ではないため、反対される場合もあるようです。
また、直葬は基本的に身内で行うため、故人の友人、知人の中には、故人とお別れをする機会がなく、残念に思う人もいることでしょう。そのような方に対しては、弔問を受けるなど気配りをしましょう。
菩提寺に直葬で行うことを相談しておく
お付き合いのあるお寺がある方は、通常そのお寺の考えのもと葬儀、火葬、そして菩提寺(ぼだいじ)に納骨をします。しかし、直葬の場合は、菩提寺を介さずに葬儀が行われるため、事前に知らせておかないと、後で菩提寺とトラブルになってしまい、先祖のお墓に納骨を許可してもらえないこともあります。菩提寺との関係を損なわないためにも、事前に相談をしておきましょう。
事前に直葬に対応している葬儀社に相談する
すべての葬儀社が直葬に対応しているわけではありません。対応してくれる葬儀社を調べ、事前に相談しておくことが大切です。
中には金額設定を高めにしていたり、提示された金額には直葬を行うための十分な物品やサービスが含まれていなかったりといったことがあります。平均的な直葬の金額を頭に入れておきましょう。
「小さなお葬式」の直葬のプラン
「小さなお葬式」では、直葬で故人をお見送りする「小さな火葬式」プランをご用意致しております。直葬に必要なものがセットになったプランです。
| 「小さな火葬式」プランに含まれているもの |
|
●寝台車での搬送2回分(病院~安置場所、安置場所~火葬場)
● 安置施設使用料・ドライアイス(3日分) ● 棺 ● 棺用布団 ● 骨壺・骨箱 ● 仏衣一式 ● 枕飾り一式 ● お別れ用花束 ● 白木位牌 ● 運営スタッフ ● 役所・火葬場手続き代行 |
火葬式プランの主な流れは、ご臨終→お迎え・安置→納棺・出棺→火葬です。詳しくは下記のページをご覧ください。

<関連記事>
【第1回調査】直葬にかかる費用相場(全国編)
直葬か他の葬儀かを決める際のポイント
直葬はシンプルな葬儀で流行っていますが、相談もせず勝手に直葬を選択すると周囲の人が気分を害するかもしれません。トラブルのもとになってしまうため注意が必要です。
何をもとに直葬にするか、他の葬儀の形式を選択するのかを以下にまとめました。ぜひ参考にした上で、故人を快くお見送りする機会を設けてみましょう。
費用に応じて決める
直葬を選択するときは、費用について考えておくようにしましょう。初めて葬儀を行う人にとっては想像以上に大きなお金が必要となることに驚くこともあります。経済的な負担が心配となり、精神的な余裕がなくなる恐れもあるでしょう。
どのくらいの費用までであれば余裕をもって賄うことができるのか、計算しておくことが大切です。
一方で直葬のメリットは、経済的な負担を軽減できることです。費用の点からも直葬の方が安心だという方は、こちらの形式を選ぶことをおすすめします。負担を軽減して安心してお見送りできるため、親族も安心できます。
大切な人を安心して見送られるよう、心配なことを少しでも減らしておくことが重要です。遺族とも相談した上で、費用を考えて決めましょう。
生前の本人の希望や家族の意見に応じて決める
直葬にするのか他の形式にするのかは、自分ひとりで決めるものではありません。一人で決めてしまうと、遺族にとっては気に入らないものになる恐れがあります。特に直葬を選択する場合は、世間から見た一般的な葬儀とは異なるため、事前に了承を得ておくことが重要です。
直葬では、故人と関係が深かった親族を中心にお見送りをすることになるため、何の相談もなく話を進めてしまうと、葬儀当日にあまり良くない雰囲気になるかもしれません。
全員が納得して安心して故人をお見送りできるように、親族と相談した上で形式を決定しましょう。大切な機会ですので、必要以上にコミュニケーションを取って、当日までの話を進めていくようにすることが大切です。
葬儀社に相談して決める
直葬をしようと思ったタイミングで、葬儀社に相談してみることもおすすめです。なぜかというと、事前に相談しておかないと、品物やサービス内容で思っていたものと違うという事態になってしまう恐れがあるためです。直前になってそのようなトラブルが発生すると、落ち着いてお見送りすることが難しくなってしまいます。
しかし、早い段階で相談しておくことで、費用やサービス内容について詳しく聞くことができます。事前に葬儀社と話し合うことで、プロの意見を取り入れながら親族での話し合いを進められるため、トラブルが生じてしまう可能性も低くなるでしょう。
何か不安なことや心配なことが出てきても、早いうちから相談することでトラブルを未然に防げます。近くの葬儀社で事前に相談し、費用や進行、スケジュールについて把握しておくと、安心して話を進めていくことができるでしょう。
<関連記事>
直葬にお布施は必要?金額の相場や渡す際のマナーを紹介します
「直葬」とはどんな葬儀形式?費用の相場や注意点とは?
直葬でも戒名は必要? | 判断方法や付け方を紹介
直葬の香典はどうする?金額の相場や渡し方など気を付けるべきマナーをチェック
直葬での服装は?平服と言われたときの理想の格好やNGな格好も紹介
直葬でのマナーまとめ!服装・香典・直葬を行うときの注意点とは?
直葬で納骨が断られる可能性がある!断られたときの対処法は?
直葬と密葬の違いは?それぞれの葬儀に決める理由や流れとは
小さなお葬式で葬儀場をさがす
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。※2024年4月 自社調べ
まとめ
葬儀に関するご準備は事前に行うことが大切です。いざという時困らないように、葬儀全般に関する疑問は、「小さなお葬式」へお問い合わせください。24時間365日専門スタッフがお客様のサポートをさせていただきます。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



初盆(はつぼん)とは、亡くなった方の忌明け後、最初に迎えるお盆のことです。ホゥ。