親の死という悲しみを抱えたまま、不慣れな手続きや準備をするのは難しいことです。親が亡くなってからどのような手続きが必要なのか、事前に知りたい方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では親が亡くなったときの相続や手続き、確認すべき書類、お通夜から四十九日法要後までの流れをご紹介します。この記事を読んでお通夜からお葬式、四十九日法要までの流れや必要なことを知っておけば、心身ともに辛い状況でもスムーズに手続きを進められるでしょう。
<この記事の要点>
・親名義の銀行口座は、死亡したことを銀行へ伝えてから初めて凍結される
・死亡届や火葬許可証など、その他期限のあるさまざな書類を役所や関係機関に提出
・相続関係の手続きは3か月~4か月以内に行う
こんな人におすすめ
親が亡くなったあとの手続きについて知りたい方
葬儀から法要までの流れを知りたい方
相続について知りたい方
親が亡くなったらまずすること
親が亡くなったらまず「死亡診断書」または「死体検案書」を医師に発行してもらいます。そのためには親が亡くなったことを医師に連絡することが必要です。
亡くなった場所が自宅か病院か、死亡原因が療養中の病気か否かで連絡先が異なります。それぞれのケースで何をしなければならないかをご説明しましょう。
自宅で亡くなった場合
療養中の病気が原因で亡くなったときは、かかりつけの病院の医師に連絡をして自宅で死亡診断書を作成してもらいます。療養中以外の病気で死亡したときは、119番か警察に連絡してください。死因を明らかにするため警察医が検視(検案)を行い、事件性がなければ行政解剖、事件性があれば司法解剖をし、死体検案書が発行されます。発行には時間がかかるので、葬儀の日程を調整する必要性が出てきます。事前に発行までの所要時間を聞いておくといいでしょう。
病院で亡くなった場合
病院で亡くなった場合の死亡診断書や死体検案書は、主治医や病院の医師によって発行されます。今後、死亡保険請求手続きや他の手続きにも必要になってくるので、複数枚コピーをとっておいてください。
親が亡くなった当日にすること
親が亡くなったことを親族、親の職場、友人、菩提寺などに連絡します。自分の職場にも報告し、忌引休暇や仕事の引継ぎなども済ませましょう。
お通夜、葬式、法要などの対応を1人で行うのは大変です。親族や友人など、親しい関係者には都合を聞き、可能であればお手伝いをお願いします。頼れる人がいれば、心にもゆとりを持てるでしょう。
葬儀社を決める
葬儀社は前もって決めておくことをおすすめします。亡くなってから葬儀社を探す場合は、費用面をしっかり説明してくれる信頼できる葬儀社を選ぶようにします。また、亡くなった先の病院が紹介する葬儀社は、料金が高額になるケースがあるので気を付けましょう。
葬儀社は参加する人数や内容の違いによってさまざまプランを用意しています。たとえば参加者が家族中心で30人程度の小規模な家族葬や、故人の親族に加えて友人、会社関係者なども参加する一般葬などです。中には通夜や告別式をせず、火葬のみプランもありますから、自分たちの意思でふさわしい葬儀社を選びましょう。
<関連記事>
後悔しない葬儀社の選び方について徹底解説!選び方のポイント・タイミングは?
ご遺体の安置場を確保する
病院の安置室は数時間しか使用できませんから、その後は自宅に搬送して安置するか、葬儀社で安置してもらうか選ばなければなりません。事前に葬儀社が決まっている場合は、死亡の連絡を入れれば、ご遺体を搬送してくれます。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
親が亡くなった時の銀行口座
親が亡くなると、親名義の銀行口座は親族が銀行に死亡したことを伝えることで初めて凍結されます。
銀行口座は、親が亡くなった後に勝手に凍結されるわけではありません。親が亡くなったときにどのような流れや理由で銀行口座が凍結されるのか、また、凍結された口座を引き継ぐ方法については以下で詳しく解説しています。
<関連記事>
親が亡くなったら銀行口座が凍結されるって本当?
親が亡くなったら確認すべきこと
亡くなった後のことを生前に話すのは、躊躇する方も多いでしょう。しかし、いざそのときになると故人の希望が分からずに悩んでしまうことがあります。
そのようなときに亡くなった親がエンディングノートや遺言を残していれば、葬儀や財産分与について故人の遺志を確認することができます。
エンディングノートに希望を書いていないか
エンディングノートは生きている間に、葬儀やお墓、相続などについて自分の意思を記したものです。葬儀の準備を始める前に読んでおきましょう。葬式の規模や参列者の希望、喪主を任せたい人、葬儀社や寺院、霊園の連絡先などが書かれている場合があります。
エンディングノートの確認が葬儀後になると、故人の遺志に沿うことができなかったと後悔してしまうかもしれません。
<関連記事>
エンディングノートの書き方まとめ
小さなお葬式で葬儀場をさがす
遺言書を残してないか
故人が遺言書を残しているならそれも確認します。金庫の中、タンスや仏壇の引き出しなどにしまわれていることもあるようです。
遺言書は見つけても勝手に開封することができません。家庭裁判所に提出し、相続人などの立会いのもとで開封、内容を確認する「検認」と呼ばれる手続きをします。ただし遺言書が公証人により作成された公正証書であれば、検認の必要はありません。
家庭裁判所に検認の申立書を提出してから、検認が行なわれるまでには1ヶ月~2ヶ月くらいかかります。相続手続きをスムーズに行うためにも、遺言書の保管場所は事前に確認しておきましょう。
葬儀から法要までの流れ
お通夜から葬儀、四十九日の法要、そしてその後にも、決めなければならないことや必要な手続きがたくさんあります。親を失った悲しさと予想以上の忙しさで必要な対応を忘れたり、誤った判断をしたりしてしまうかもしれません。
そのため葬儀社と相談するときには、喪主を務めた経験があるなど、信頼できる親族に同席してもらうことをおすすめします。
1. 葬儀社との打ち合わせ
葬儀社との打ち合わせではまず葬儀の日程、場所、時間を決めます。お寺や斎場、火葬場の空き状況、参列者の予定などを考慮して決定しましょう。
葬儀の日程が決まったら、関係者に日程を知らせます。電話やFAX、メール、自治会の掲示板などを利用しましょう。知らせる範囲は葬儀の規模によって変わります。
葬儀には喪主、連絡係、弔辞を述べる方、受付係、会計係などが必要です。葬儀社との打ち合わせではその役割分担も決めます。弔辞をお願いする方には事前に連絡をしておきましょう。
さらには祭壇や花をどうするか、参列者への会葬御礼品、遺影の選択、通夜振る舞いや精進落としなどの会食メニュー、遠方からの参列者の宿泊手配、火葬場までの送迎バスの手配なども決めていきます。
2.お通夜を執り行う
お通夜は、葬儀・告別式の前日に行われます。一般的なお通夜の流れは次の通りです。
1. 受付が開始され、受付が終わった弔問客は斎場の案内に従い席につきます。
2. 喪主、遺族、参列者が着席後、僧侶の入場となります。
3. 僧侶の読経が始まり、焼香をします。喪主、遺族、親族、弔問客の順で行います。
4. 焼香が終わると僧侶による説法、その後僧侶が退場されます。
5. 喪主が弔問客に挨拶をします
6. 通夜振る舞い
喪主が会食前か後に挨拶をし、弔問客への感謝の意を表します。
<関連記事>
お通夜とは|基礎知識と遺族側・参列者側が知っておくべきマナー
3.葬儀・告別式を執り行う
葬儀・告別式はお通夜の翌日に行います。弔電の確認と読み上げる順番や、生花の並べ方を決めておきましょう。葬儀・告別式の流れはお通夜と基本的に同じです。
1. 受付が開始され、弔問客は席に着きます。
2. 喪主、遺族、参列者が着席後、僧侶の入場となります。
3. 僧侶の読経と焼香を行います。弔電の読み上げをします。
4. 僧侶による説法、その後僧侶が退場されます。
5. 喪主の挨拶と出棺
親族、弔問客が棺に生花を納めた後、棺に蓋がされ、喪主が挨拶を述べます。その後、出棺となり火葬場へ向かいます。葬儀社に火葬許可証を渡しておきましょう。
6. 火葬と骨上げ
火葬場で僧侶に読経してもらい、焼香後、火葬となります。火葬にかかる時間は約1~2時間です。
<関連記事>
葬儀は段取りが肝心。流れ・費用・マナーが「やさしくわかる!」
4.初七日と式中初七日法要
本来、初七日は亡くなった日から7日目に行う法要ですが、最近は葬儀の式中に初七日を行うことが多くなりました。お寺や葬儀を手伝っていただいた方などへの御礼、挨拶は初七日までにしておきましょう。
5.四十九日法要
亡くなって四十九日で魂が旅立つと言われ、忌明けの法要を行います。親族がお寺やお墓に赴き、僧侶が読経を行います。四十九日は重要な法要であり、多くの方を招くため、しっかりとした準備が必要です。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
親が亡くなったらやる「手続き」
親が亡くなった後に行うのはお葬式などの儀式だけではありません。さまざまな書類を役所や関係機関に提出することも必要です。
どこにどんな書類を、いつまでに提出するのかをご紹介します。提出期限が決まっているものもあるので参考にしてください。
7日以内に死亡届と火葬許可証の手続きをする
死亡届の提出と火葬許可証は、死亡を確認してから7日以内という期限があります。死亡届を提出しないと「火葬許可証」が発行されないので、葬儀の準備をスムーズに進めるためにもすぐに手続きしましょう。
死亡届は故人の死亡地や本籍地、届出人の所在地(住所地)の役場に提出します。死亡届の用紙はA3サイズで左半分が死亡届、右半分が死亡診断書(死体検案書)です。必要事項を記入して提出しますが、提出の際には印鑑と身分証明書を忘れないようにしましょう。
役所へ提出した死亡届は手元に帰ってきません。死亡後の手続きでは死亡届や死亡診断書の提示が必要なこともあるので、コピーを数枚取るようにしましょう。
役所の窓口で死亡届が受理されると火葬許可証が受け取れます。火葬後には、それに火葬執行証明済みの印が押され、それがいわゆる埋葬許可証です。
亡くなってから2週間以内にやるべき手続き
死亡届より提出期限が短いのが社会保険です。亡くなった親の勤務先の事業主が、5日以内に「被保険者資格喪失届」を提出しなければなりません。
年金を受け取っていた場合、厚生年金と共済年金の受給停止手続きは10日以内、国民年金は2週間以内に受給停止の手続きをします。
ただし故人のマイナンバーが日本年金機構に登録されていれば、届出は原則不要です。届出が必要な場合は、「年金受給権者死亡届(報告書)」に必要事項を記入し、死亡を証明する書類と年金証書を添えて年金事務所もしくは街角の年金相談センターに提出します。
ほかにも、世帯主変更届、国民健康保険証資格喪失届、後期高齢者医療保険の資格喪失届、介護保険資格喪失届を2週間以内に役場に提出しなければなりません。こうした手続きは期限を待たずになるべく早く行いましょう。
期限のあるその他の必要な手続き
故人が加入していた保険の種類により、「葬祭費」もしくは「埋葬料」が支給されます。国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していたら葬祭費、健康保険に加入していた場合は埋葬料です。
葬祭費は「葬儀を執り行った日の翌日から2年以内」に申請しなければ支給されません。葬式後に故人の保険証を返却する手続きなどと合わせて、市区町村役場の国民年金課や後期高齢者資格係などで手続きしましょう。
埋葬料は勤務先や社会保険事務所に申請します。故人の「亡くなった翌日から2年以内」が申請期限です。
遺族年金を受け取る場合も申請をしましょう。故人が国民年金加入者なら市区町村の役所にある国民年金課で、厚生年金に加入していたなら社会保険事務所で手続きをします。
遺族年金の申請を忘れた場合、受給権が発生してから5年以内は請求可能です。しかし5年を超えると時効により権利が消滅します。遺族年金を受け取る場合も故人が亡くなってからできるだけ早く請求しましょう。
期限はないが早いほうがよいもの
以下のものもそれぞれ対応が必要です。
・シルバーパス→市区町村役場
・運転免許証 → 警察
・死亡退職届 → 勤務先
・死亡退職金 → 勤務先
・最終給与 → 勤務先
・クレジットカード → クレジットカード会社
・負債の確認 → 金融機関やローン会社
・電話加入権 → 電話会社
・光熱費(電気、ガス、水道)→ 契約会社、水道局
親が亡くなった直後は来客や葬儀準備など、そのときに対応しなければならないものが多いため、期限がないものは後回しにしがちです。しかし、ほっとひと息ついたころには後回しにしていたことを忘れてしまうこともあります。必要な手続きはできるだけ早く終わらせましょう。
親が亡くなった時の「相続」について
相続手続きも、親が亡くなった後に行わなければならない大切な手続きです。「葬儀の後にお金の話をするのはいかがなものか」という気持ちもあるでしょうが、親族が揃う貴重な機会なので今後の流れや手続きについて相談しましょう。
相続自体に期限はありませんが、相続に関係する法的手続きには期限が定まっているものもあるので注意が必要です。
速やかに手続きが必要なもの
「相続人の確定」と「遺言書の検認」はできるだけ早く行う必要があります。遺言書の検認については前述しましたが、公正証書以外の遺言書は相続人であっても、家庭裁判所の検認なしに開封、遺言手続きの実行をしてはなりません。家庭裁判所の検認手続きが終了してから、不動産の名義変更や預貯金の名義変更などの相続手続きに移行できます。
相続は相続内容が決まってからの手続きに手間や時間がかかりますから、相続内容を決めるための相続人の確定と遺言書の検認は速やかに行いましょう。
相続放棄は3ヶ月以内
「相続放棄」の手続きは相続開始を知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません。相続放棄の一般的な理由としては、故人に財産を上回る多額の借金があり、相続すると借金を抱えるのと同じになるというものです。
こうした状態で相続人が相続放棄を忘れると、否応なしに借金を引き継ぐことになります。もし相続放棄できる3ヶ月が過ぎてしまったら、すぐに弁護士に相談し、債権者への対応を一任するのが賢明でしょう。
準確定申告は4ヶ月以内
「準確定申告」とは1年の途中で亡くなった方の所得の申告と納税を、相続人が行うことです。1月1日から故人が亡くなった日までの所得が対象になります。
しかしすべての故人が準確定申告の対象になるわけではありません。対象条件は確定申告と同じで、給与所得以外に20万円以上の収入があること、事業所得や不動産所得があることなどです。
確定申告期間は毎年2月16日から3月15日ですが、準確定申告は故人の死亡を知ってから4ヶ月以内に相続人全員で行います。申告書の提出先は、故人の住所があった管轄税務署です。
相続税の申告は10ヶ月以内
相続税の申告は相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行います。遺産を相続する全員がこの期間内に行うのは、相続税申告書を管轄の税務署に提出することと相続税の納付までです。
もし期間内に申告と納付がなければ「無申告加算税」「延滞税」という罰則が加えられます。相続に関係する法的手続きは速やかに行いましょう。
遺品の整理・お部屋の片づけが必要な方へ
小さなお葬式では、故人様のお荷物の整理、お部屋の片づけや掃除などを行う「遺品整理」サービスをご用意しています。お見積りは完全無料!料金にご納得いただけた場合のみのご依頼なので安心です。また、急いで片づけなければいけない、見積りや作業に立ち合えない、予算に余裕が無いなどのご相談も可能です。まずは以下からお問い合わせください。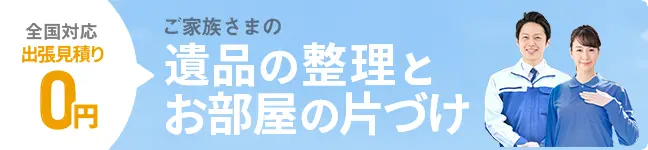
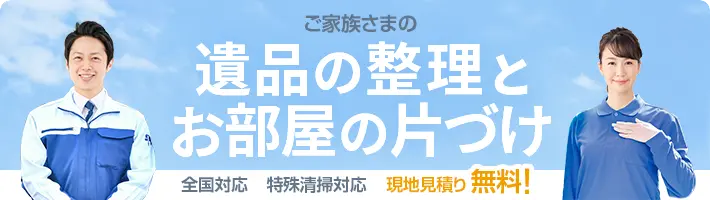
<関連記事>
親が亡くなったらするべき相続手続きまとめ!手続きの期限にも注意
小さなお葬式で葬儀場をさがす
親が亡くなった時の香典は?
親が亡くなったときに香典を出すかどうかで迷っている人もいるでしょう。香典とは弔意を表する金銭で、葬儀に参列する人が故人の親族に対して渡すものです。
親が亡くなった場合は喪主として葬儀を執り行うことも多く、香典を出す必要がないのではないかと考えるかもしれません。
結論からいうと、親が亡くなった場合は基本的に香典を出す必要はありません。喪主として葬儀を執り行う場合は、香典を受け取る立場になります。
<関連記事>
親が亡くなったら香典を出したほうがいいの?
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。※2024年4月 自社調べ
まとめ
親が亡くなったらやることについて説明しました。お通夜や葬式の準備だけでなく、役所に提出する書類の用意、相続に関する手続きなど、葬儀後もたくさんの対応が必要です。
全体の流れを把握すれば不安は多少軽減されますが、1人ですべてを行うのは大変です。親族や友人の協力を得ながら、専門家のサポートがあればさらに助かるでしょう。小さなお葬式は葬儀前から葬儀後までのさまざまなサポートをご用意しております。どうぞお気軽にお問い合わせください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


よくある質問
親が不慮の事故で亡くなった場合はどうすればいいの?
亡くなったあと銀行口座が凍結されるの?
親が亡くなったとき会社はどれくらい休めるの?
親が生命保険に入っていた場合はどうしたらいい?
香典返しはいつすればいいの?
お墓がまだないときはどうすればいいの?

私的年金制度は公的年金に上乗せし保険料を支払うと受給できる、任意で加入する年金制度です。ホゥ。





























